症例は11歳女児。4歳時にインフルエンザ罹患時に熱性痙攣の既往あり。海外渡航歴なし。7月21日、夕方より40℃台の高熱、咳嗽を認め、7月22日、近くの医療機関を受診し、簡易検査でインフルエンザA型陽性で、ザナミビルが処方され、1回10mg 1日2回吸入を開始した。同日の夜間40〜41℃台の高熱が持続し、異常言動(突然笑う、わけのわからないことを言う、突然動き出す)を認めた。医療機関へ向かう途中の車中で意識混濁(開眼しているも、視点が合わず、呼応なし)、数十秒の強直性痙攣を3回繰り返し、7月22日、当院に入院となった。意識レベルは、JCS(Japan Coma Scale)で3〜20程度であった。
血液検査所見は、WBC 5,300/μl(Neutro. 68.0%、Lympho. 30.0%)、Hb 14.0 g/dl、Plt 19.3万/μl、AST 24 IU/l、ALT 9 IU/l、LDH 220 IU/l、BUN 8.0 mg/dl、Cr 0.63 mg/dl、CK 92 IU/l、Na 136 mEq/l、K 3.3 mEq/l、Cl 100 mEq/l、CRP 2.18 mg/dl、フェリチン 113 ng/ml、IL-6 7.9 pg/ml(正常≦4.0)、TNF-α 0.9 pg/mlと、サイトカインは軽度の高値で、血液所見で大きな異常を認めなかった。髄液所見は、細胞数 2/μl(Lympho. 2)、蛋白24 mg/dl、糖 71 mg/dl、IL-6 6.6 pg/ml、TNF-α 0.5 pg/ml以下と、細胞数の上昇を認めなかった。採取した鼻咽腔ぬぐい液を国立感染症研究所のマニュアルに示された方法に従い、宇都宮市衛生環境試験所でリアルタイムRT-PCR検査を実施した。A型共通のM遺伝子およびAH1pdm HA遺伝子を確認し、新型インフルエンザA(H1N1)と診断した。
入院処置中は鎮静を保てず、不平不満を口にした。後に確認したところ、本人は入院からここまでのエピソードはほとんど記憶に残っていなかった。その後2時間の間に、数十秒の痙攣をさらに5回繰り返し、意識レベルが悪化した。ジアゼパム静注を行い、以降痙攣は消失した。同時にステロイドパルス療法(メチルプレドニゾロン 1g/日 3日間)開始した。入院当日の7月22日(第3病日)に脳波および頭部MRIを施行した。脳波では、基礎波が不規則で、やや高振幅の徐波を全般性に認めた。頭部MRIでは、脳梁膨大部にT2WIで高信号を認め、拡散強調画像(DWI)でも脳梁膨大部に限局して高信号を認めた(図1)。7月23日より解熱傾向となり、7月24日以降発熱なく、意識レベルは完全に回復した。7月26日(第6病日)に頭部MRIを再度施行し、脳梁膨大部病変は消失していた(図1)。7月29日(第9病日)に神経学的後遺症なく退院となった。8月5日(第16病日)の脳波所見で、左側前頭部優位に全誘導にわたって棘徐波を認めた(図2)。現在、てんかんの発症に留意し、経過観察中である。
考察:インフルエンザの一過性の脳梁膨大部病変は2004年に初めて報告 3)されて以来、同様の症例の報告が相次いでいる。一過性のため血管性浮腫が考えられていたが、DWIで拡散低下を伴うため、過剰な免疫反応による細胞障害性による浮腫の機序も考えられており、いまだ不明な点が多い。脳梁は左右の大脳半球をつなぐ交連線維の束であり、左脳と右脳の情報の交通を司っている。脳梁膨大部は主に後頭葉から線維が伸びており、後頭葉は空間の認識や言語機能に大きな役割を果たしていることから、脳梁膨大部病変により左右の情報の交通が遮断されることで、本例のようなせん妄における幻覚や見当識障害、異常言動を誘発する可能性が示唆されている。また本例では、意識レベルが完全に回復したときには、脳梁膨大部病変は消失しており、臨床症状と合致していた。新型インフルエンザは、特に若年者で免疫反応が過剰に働くことが示唆されているため、今後の動向に留意すべきと考えられた。
参考文献
1) Morishima T, et al ., Clin Infect Dis 35: 512-517, 2002
2)CDC, MMWR 58(28): 773-778, 2009
3)Takanashi J, et al ., AJNR Am J Neuroradiol 25(5): 798-802, 2004
独立行政法人国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科臨床研究部 山口禎夫
同院小児科 植田恵介 北原 望 石井 徹
自治医科大学感染制御部 森澤雄司
北里大学抗感染症薬研究センター 花木秀明
北里大学北里生命科学研究所大学院 感染制御科学府 砂川慶介
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)
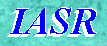
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る
