 発生動向総覧 発生動向総覧
*2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。
◆全数報告の感染症
〈第29週コメント〉 7月25日集計分
注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。
*感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。
| 1類感染症: |
報告なし |
| 2類感染症: |
結核 204例 |
| 3類感染症: |
:細菌性赤痢11例(感染地域:広島県8例*、中国2例、フィリピン1例)
*保育園における集団発生
腸管出血性大腸菌感染症118例(うち有症者82例、うちHUS 4例)
|
感染地域:すべて国内
国内の多い感染地域:大阪府18例*、東京都13例、兵庫県9例、神奈川県6例、千葉県6例
*うち5例は保育園における集団発生
年齢群:10歳未満(42例)、10代(7例)、20代(22例)、30代(13例)、40代(10例)、50代(12例)、60代(4例)、70歳以上(8例)
血清型・毒素型:O157 VT1・VT2(48例)、O157 VT2(38例)、O26 VT1(12例)、O111 VT1(5例)、O103 VT1( 2例)、O103 VT1・VT2(2例)、O18 VT2(1例)、O145 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、その他/不明(8例)
|
|
| 4類感染症: |
つつが虫病1例(感染地域:青森県)
デング熱2例(感染地域:カンボジア1例、スリランカ1例)
日本紅斑熱2例(感染地域:和歌山県1例、鹿児島県1例)
マラリア1例(三日熱_感染地域:インドネシア)
| レジオネラ症18例(すべて肺炎型) |
|
年齢群:50代9例、60代6例、70代2例、80代1例
感染地域:静岡県3例(うち1例温泉)、埼玉県2例、愛媛県2例、北海道1例、秋田県1例、福島県1例、群馬県1例、東京都1例、宮城県1例、長野県1例、福井県1例、兵庫県/奈良県1例、国内(都道府県不明)1例、中国1例
|
|
| 5類感染症: |
| アメーバ赤痢6例(すべて腸管アメーバ症) |
|
感染地域:国内5例、中国1例
感染経路:経口1例、性的接触2例(ともに同性間)、不明3例
|
| ウイルス性肝炎3例 |
|
B型2例_感染経路:性的接触1例(同性間)、感染者の介護1例
C型1例_感染経路:不明
|
急性脳炎1例(病原体不明.50代)
クロイツフェルト・ヤコブ病2例(ともに孤発性プリオン病古典型)
後天性免疫不全症候群14例(AIDS 6例、無症候7例、その他1例) |
|
感染地域:国内11例、タイ2例、ブラジル1例
感染経路:性的接触11例(異性間7例、同性間3例、異性間/同性間1例)、不明3例
|
梅毒9例(早期顕症I期3例、早期顕症II期1例、無症候5例)
破傷風1例(60代)
バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型:VanC 1例_菌検出検体:血液、遺伝子型:不明1例_菌検出検体:便)
(補)他に報告遅れとして、細菌性赤痢4例(感染地域:東京都1例、インドネシア1例、インド1例、南アフリカ1例)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(40代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型:不明_菌検出検体:尿)等の報告があった。
|
◆定点把握の対象となる5類感染症(週報対象のもの)
全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000 カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500 カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
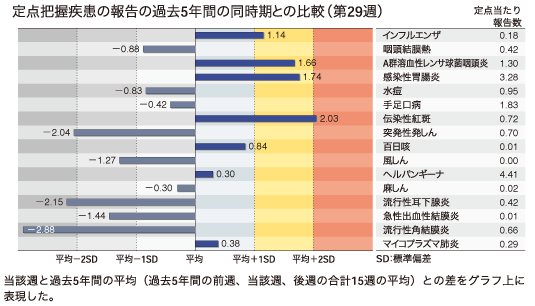
インフルエンザ:定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では沖縄県(12.10)、宮崎県(0.32)、福島県(0.30)が多い。
小児科定点報告疾患:RSウイルス感染症は145例の報告があり、報告数は減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約72%を占めている。咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では埼玉県(0.90)、滋賀県(0.81)、長野県(0.76)、青森県(0.71)が多い。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第23週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では埼玉県(2.6)、山形県(2.1)、北海道(2.1)、茨城県(2.0)が多い。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では大分県(7.3)、福井県(6.6)、滋賀県(4.8)、宮崎県(4.8)が多い。水痘の定点当たり報告数は25週以降減少が続いている。都道府県別では宮城県(1.8)、長野県(1.5)、福井県(1.5)が多い。手足口病の定点当たり報告数は微減した。都道府県別では和歌山県(13.7)、福島県(6.7)、福岡県(4.8)、熊本県(4.4)が多い。伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では長野県(3.8)、新潟県(2.5)、宮城県(2.4)が多い。百日咳の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では栃木県(0.06)、静岡県(0.05)、京都府(0.05)、徳島県(0.04)が多い。風しんの報告数は10例と微増した。都道府県別では京都府、大阪府、福岡県、大分県から各2例、茨城県、岡山県から各1例の順であった。ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では三重県(9.8)、宮崎県(8.6)、徳島県(8.4)、兵庫県(8.4)が多い。麻しんの報告数は減少し、21都道府県から64例の報告があった。都道府県別では大阪府15例、埼玉県、神奈川県、福岡県から各7例、東京都5例、静岡県3例、青森県、宮城県、茨城県、奈良県、広島県から各2例の順であった。流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では宮崎県(1.03)、愛媛県(0.97)、大分県(0.94)、が多い。
基幹定点報告疾患:マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.6)、福島県(2.0)、宮城県(1.3)が多い。成人麻しんの報告数は増加し、15都道府県から28例の報告があった。都道府県別では、福岡県6例、宮城県、東京都、神奈川県から各3例、千葉県、大阪府から各2例、北海道、岩手県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、新潟県、愛知県、広島県から各1例の順であった。
(補)風しん(茨城県)および麻しん(京都府)の報告は修正予定であり、これをふまえてコメントしている。
 注目すべき感染症 注目すべき感染症
◆ インフルエンザ
インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスの感染による急性の呼吸器感染症である。感染を受けてから1〜3日間の潜伏期間を経て、発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然出現し、咳・鼻水などの上気道炎症状がこれに続き、1週間前後の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザの症状であり、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強い。高齢者では超過死亡の原因として知られている二次性の細菌性肺炎、小児では発症率は低いものの生命に関わる可能性のあるインフルエンザ脳症等の合併症が知られている。例年わが国では冬季を中心に膨大な数の罹患者が発生しているが、最近では春季及び夏季の地域的な流行も観察されている。
感染症発生動向調査によると、今シーズン(2006/07シーズン)のインフルエンザの流行は2007年の第3週(定点当たり報告数1.06)より開始し、そのピークは8週後の第11週(定点当たり報告数32.94)であった(図1)。その後患者発生数は全国的には一貫して低下していたが、北海道、東北地域では春期休暇明けの第15週より再流行がみられ、また沖縄県では患者発生報告数が大きく低下しないままに第21週以降再び増加し、第25週以降現在に至るまで定点当たり報告数が10.0を超えた状態が継続しているのは、昨シーズンと同様である。特に、沖縄県における夏季を中心としたインフルエンザの再流行は、2004/05シーズン以降3シーズン連続してみられている現象である(図2)。全国約4,800カ所のインフルエンザ定点医療機関からの第29週のインフルエンザ定点当たり報告数は0.18(報告数815)となり、前週の0.21よりも低下がみられた(図1)。都道府県別では、沖縄県(12.10)、宮崎県(0.32)、福島県(0.30)、宮城県(0.18)、岩手県(0.08)、熊本県(0.08)の順であり、沖縄県の報告数が突出した状況が続いている(図3)。2006年第36週以降これまでの定点医療機関からの定点当たり累積報告数は230.36(総患者累積報告数1,074,364)であり、都道府県別では沖縄県(449.17)、宮崎県(390.39)、福岡県(346.00)、大分県(331.66)、新潟県(304.45)、愛知県(297.43)、福井県(292.78)の順となっており、シーズン全体を通してみると九州及び中部地域での流行が比較的大きかった(図4)。累積報告数の年齢別割合では、5〜9歳32.1%、0〜4歳21.5%、10〜14歳20.4%の順となっている(図5)。
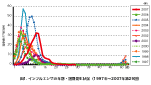 |
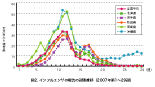 |
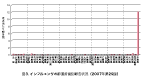 |
|
図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1997年〜2007年第29週)
|
図2. インフルエンザの報告の週別推移(2007年第1〜29週)
|
図3. インフルエンザの都道府県別報告状況(2007年第29週)
|
2006年第36週以降これまでに全国の衛生研究所から報告されたインフルエンザウイルス分離報告(総報告数4,976)では、AH1亜型(Aソ連型)11.6%(報告数577)、AH3亜型(A香港型)47.6%(報告数2,370)、B型40.8%(報告数2,029)であり、AH3亜型とB型を合わせた分離報告割合が90%近くを占めている(図6)。また、沖縄県では第21週以降に20件のウイルス分離報告があり、ウイルス型別ではそれぞれAH1亜型8、AH3亜型3、B型9の報告数となっている。
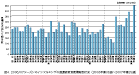 |
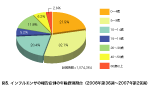 |
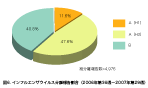 |
|
図4. 2006/07シーズンのインフルエンザの都道府県別累積報告状況(2006年第36週〜2007年第29週)
|
図5. インフルエンザの報告症例の年齢群別割合(2006年第36週〜2007年第29週)
|
図6. インフルエンザウイルス分離報告割合(2006年第36週〜2007年第29週)
|
今シーズンのインフルエンザの流行は2007年第3週より開始し、第11週にピークを迎え(定点当たり報告数32.94)、その後全国的には報告数の減少が続いたが、第15週以降に北海道、東北地域で春季の流行の再燃がみられ、また第21週以降には沖縄県で夏季の流行がみられている。これら春季、夏季のインフルエンザの地域的な流行は今シーズンのみの現象ではなく、わが国においてもインフルエンザの流行の時期は冬季を中心とした限定的なものであると考える べきではない。次シーズン以降も、特に多くの学校等が夏期休暇に入るまでの期間は、インフルエンザの発生動向には注意が必要であると思われる。
◆ 百日咳
百日咳は、好気性のグラム陰性桿菌である百日咳菌(Bordetella pertussis)の感染を原因とする急性の呼吸器感染症である。特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴としており、母親からの移行抗体が有効に働かないために乳児期早期から罹患する可能性があり、ことに生後6カ月以下では死に至る危険性がある疾患である。
通常は感染後7〜10日間の潜伏期間を経て発症するが、臨床経過は(1)カタル期、(2)痙咳期、(3)回復期の3つに分けられている。以下にそれぞれの経過につて記す。
(1)カタル期(1〜2週間):感冒様症状で始まり、合併症がない限り発熱はない。次第に咳が増強して1〜2週のうちに痙咳期に移行していく。初期は感染力が強い。
(2)痙咳期(2〜3週間):次第に特徴ある発作性痙攣性の咳(痙咳)となる。短い咳が連続的に発生し(スタッカート)、続いて息を吸い込む時に笛のようなヒューという音が出る(笛声:Whoop)。この様な咳嗽発作が繰り返され、しばしば嘔吐を伴う。発作は夜間に多く、この時期には息を詰めて咳をするために顔面は浮腫状となり、いわゆる百日咳様顔貌がみられる。幼若乳児ではこのような特徴的な痙咳発作を示さずに、無呼吸発作からチアノーゼ、けいれん、呼吸停止へと進展する場合がある。また、乳児では合併症として肺炎の他に脳症を発症することがあり、予後不良であるため要注意である。
(3)回復期(2、3週間以上):痙咳期が2〜3週間続いた後、激しい発作や嘔吐は次第に減弱して回復期に移行するが、時折発作性の咳嗽がみられ、全経過2〜3カ月で治癒に至る。
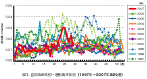 |
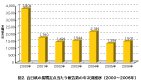 |
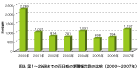 |
|
図1. 百日咳の年別・週別発生状況(1997年〜2007年第29週)
|
図2. 百日咳の累積報告数の年別推移(2000〜2006年)
|
図3. 第1〜29週までの百日咳の累積報告数の比較(2000〜2007年)
|
なお、成人の百日咳では咳が長期にわたって持続するが、典型的な発作性の咳嗽を示すことはなく、やがて回復に向かう場合が多いが、症状が典型的ではないために診断が見逃されやすく、感染源となって周囲へ感染を拡大してしまうこともあり、注意が必要である。百日咳の治療薬としての抗生物質はマクロライド系抗菌薬が第一選択であるが、セフェム系が処方されることもある。早期に抗菌薬を処方すれば、症状の軽減と菌排出期間(無治療の場合は3週間前後)の短縮が期待できる。主な感染経路は発症患者の鼻咽頭や気道分泌物による飛沫感染と接触感染である。
わが国では、現在百日咳に対する予防として、乳幼児に対して広く百日咳(P)ワクチンを含んだDPT3種混合ワクチンが実施されているが、1950年にこの百日咳ワクチンが開始されるまでは、年間10万例以上の患者発生報告があり、その約10%が死亡していた。ワクチンの普及と共に百日咳の発生数は激減しているが、未だ発病者があり、また発展途上国を中心に現在も世界各国で流行がみられている。予防接種法の改正により、1994年10月からはそれまで2歳であったDPTワクチンの接種開始年齢が生後3カ月に引き下げられたために、患者報告数は更に減少した。しかしながら、今後ワクチン接種率が低下するようなことがあると、再び流行する可能性は十分にあると思われ、接種率を高く維持することが重要である。
感染症発生動向調査によると、2007年の百日咳の週別の定点当たり報告数は、2001年以降の過去5年間の同時期と比較して高い場合が多くなっている(図1)。2000年〜2006年の過去6年間の累積患者報告数では、2000年の報告数が3,804と最も多く、次いで2004年(2,189)、2001年(1,760)の順であり、2000年と2004年以外では報告数は全て2,000以下となっている(図2)。しかしながら2000年以降2007年までの各年の第29週までの累積報告数を比較すると、2007年の報告数1,197は、2000年の報告数2,289に次ぐ値となっており、2001年以降では最も報告数が多い(図3)。2007年第29週までの定点当たり累積報告数を都道府県別にみると、栃木県(1.91)、千葉県(1.53)、沖縄県(0.97)、徳島県(0.86)、福岡県(0.77)の順となっており、特に栃木県、千葉県からの報告数が多くなっている(図4)。2000〜2007年まで(2007年は第29週まで)の年間の累積報告数の年齢別割合をみると、0歳児、1歳児を中心とした乳幼児からの報告割合は年々低下がみられている一方で、小児科定点からの報告ではあるものの、20歳以上の報告割合は年々増加しており、2007年では30.7%となっている(図5、図6)。
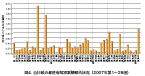 |
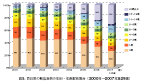 |
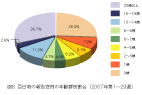 |
|
図4. 百日咳の都道府県別累積報告状況(2007年第1〜29週)
|
図5. 百日咳の報告症例の年別・年齢群別割合(2000年〜2007年第29週)
|
図6. 百日咳の報告症例の年齢群別割合(2007年第1週〜29週)
|
DPTワクチンの普及により、百日咳の患者発生数はかつてに比べて大きく減少し、流行を示す明確なピークも認められないまでになってきているといわれている。しかしながら本調査結果にもみられるとおり、あまり典型的な症状を示さない年長児例や、小児科定点からの報告ではあるものの、成人例の報告割合が無視できないほどに増加してきている。最近みられた大学における百日咳の集団発生事例の発生は、この成人例の報告数の増加をある程度反映している可能性も考えられる。百日咳の発生動向の推移には、今後とも注意が必要であるが、小児科定点からの報告のみでは、特に15歳以上の年齢層の患者発生の推移を正確に把握することは困難であるといわざるを得ない。
|

