
 | |||
|
| |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1類感染症: | 報告なし | ||||||||||
| 2類感染症: | 結核236例 | ||||||||||
| 3類感染症: | 細菌性赤痢4例(感染地域:千葉県1例、インドネシア1例、モロッコ1例、エチオピア1例) 腸管出血性大腸菌感染症39例(うち有症者20例、うちHUS 1例)
|
||||||||||
| 4類感染症: | A型肝炎2例(感染地域:福井県/ウズベキスタン1例、エジプト1例) つつが虫病29例〔感染地域:鹿児島県6例、岐阜県4例、千葉県3例、福島県2例、群馬県2例、東京都2例、神奈川県2例、広島県2例、山梨県1例、兵庫県1例、和歌山県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)1例、国外(国不明)1例〕 デング熱1例(感染地域:メキシコ) マラリア1例(熱帯熱_感染地域:ウガンダ)
|
||||||||||
| 5類感染症: |
(補)他に第47週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例(感染地域:ネパール)、レジオネラ症2例〔ともに60代_感染地域:群馬県1例(温泉)、富山県1例(温泉)〕、急性脳炎2例〔単純ヘルペスウイルス1例(40代)、病原体不明1例(9歳)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(60代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝型:VanC_菌検出検体:尿)等の報告があった。 |
||||||||||
◆定点把握の対象となる5類感染症(週報対象のもの)
全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000 カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500 カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
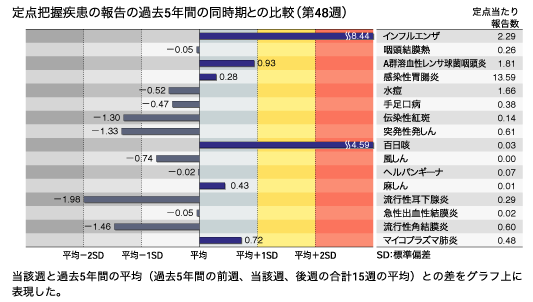
インフルエンザ:定点当たり報告数は第42週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では北海道(14.8)、岡山県(7.2)、和歌山県(6.4)、兵庫県(5.2)、青森県(4.1)、神奈川県(3.9)、千葉県(2.8)、山梨県(2.8)が多い。
小児科定点報告疾患:RSウイルス感染症は2,094例の報告があり、報告数は第42週以降増加が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約75%を占めている。咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第44週以降増加が続いている。都道府県別では青森県(1.51)、山梨県(1.13)、佐賀県(1.09)が多い。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では山口県(3.5)、埼玉県(2.9)、富山県(2.8)、石川県(2.8)が多い。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第42週以降増加が続いている。都道府県別では長崎県(34.7)、大分県(32.1)、佐賀県(29.0)、福岡県(26.7)、熊本県(26.2)が多い。水痘の定点当たり報告数は第41週以降増加が続いている。都道府県別では新潟県(3.9)、福島県(3.7)、岩手県(3.0)、宮城県(2.9)が多い。手足口病の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では鳥取県(1.42)、大分県(1.42)、島根県(1.09)が多い。伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では新潟県(0.66)、北海道(0.41)、秋田県(0.40)が多い。百日咳の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では岐阜県(0.23)、千葉県(0.16)、新潟県(0.07)、香川県(0.07)が多い。風しんの報告数は7例と増加した。都道府県別では青森県3例、宮城県、千葉県、東京都、山口県から各1例の順であった。ヘルパンギーナの定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では岩手県(0.41)、秋田県(0.26)、福島県(0.19)が多い。麻しんの報告数は増加し、10道府県から44例の報告があった。都道府県別では北海道12例、大阪府8例、神奈川県、兵庫県から各5例、青森県、千葉県、福岡県から各3例、愛知県、大分県から各2例、埼玉県1例の順であった。流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では秋田県(1.17)、新潟県(1.03)、群馬県(0.84)が多い。
基幹定点報告疾患:マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(2.7)、福島県(2.6)、宮城県(2.3)が多い。成人麻しんの報告数は横ばいであり、3府県から3例の報告があった。都道府県別では、埼玉県、神奈川県、大阪府から各1例であった。
◆ インフルエンザ
インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症であり、わが国においては、例年12月中旬もしくは1月に全国的な流行が始まり、多くのシーズンにおいて年間1,000万人以上の発病者がみられている。
臨床症状としては、インフルエンザウイルスの感染を受けてから1〜3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現われ、咳、鼻汁などの上気道炎症状がこれに続き、約1週間の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザで、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強い。とくに、高齢者や慢性疾患を持つ患者では、入院や死亡の危険が増加する。小児では中耳炎の合併、熱性痙攣や気管支喘息を誘発することもある。また近年、乳幼児を中心とした小児において、急激に悪化する急性脳症が重篤な合併症として存在することが明らかとなっている。
感染症発生動向調査によると、インフルエンザの定点当たり報告数は2007年第42週以降増加が続いており、第48週は2.29(報告数10,794)であった(図1)。都道府県別では、北海道(14.8)、岡山県(7.2)、和歌山県(6.4)、兵庫県(5.2)、青森県(4.1)、神奈川県(3.9)、千葉県(2.8)、山梨県(2.8)、埼玉県(2.7)、沖縄県(2.6)の順となっており、患者報告数の急増が続いている北海道をはじめ、より広範な地域での患者発生数の増加が目立つ(図2)。シーズン開始の第36週から第48週までの定点当たり累積報告数は6.19(累積報告数29,504)であり、年齢別では5〜9歳44.9%、0〜4歳21.6%、10〜14歳13.9%、30〜39歳7.1%の順となっており、最多を占める5〜9歳からの報告数の割合は更に増加傾向にある(図3)。第36週以降のインフルエンザウイルスの分離・検出報告数は24都道府県から265件であり、うちAH1亜型247件(93.2%)、AH3亜型16件(6.0%)、B型2件(0.8%)となっており、現時点での国内におけるインフルエンザ流行の原因ウイルスの大半はAH1亜型であると思われる(図4、図5)。
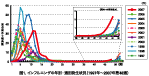 |
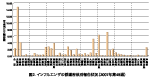 |
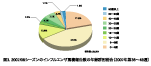 |
|
図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1997年〜2007年第48週) |
図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2007年第48週) |
図3. 2007/08シーズンのインフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2007年第36〜48週) |
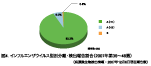 |
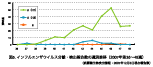 |
|
図4. インフルエンザウイルス型別分離・検出報告割合(2007年第36〜48週) |
図5. インフルエンザウイルス分離・検出報告数の週別推移(2007年第36〜48週) |
第47週に、インフルエンザの定点当たり報告数の全国平均値は、流行開始の指標である定点当たり報告数1.0を上回ったが、第48週も継続的に増加している。今後も比較的短期間のうちにインフルエンザの患者発生数は大きく増加し、より本格的な流行へと発展する可能性が高い。今後のインフルエンザの発生動向にはより一層の注意が必要である。
インフルエンザの予防の基本は、流行前にワクチン接種を受けることであり、ある程度の発病防止と罹患した場合の重症化防止に有効であると報告されている。今シーズンのインフルエンザワクチンを接種予定でまだ接種を完了していない人は、速やかに接種を完了することが望まれる。また、流行時には外出時のマスクの利用や帰宅時のうがい、手洗いは、かぜの予防と併せて奨められる。さらにインフルエンザの主な感染経路が飛沫感染であることから、インフルエンザに罹患し、咳嗽などの症状のある人は特に、周囲への感染拡大を防止する意味から、マスクの着用が推奨される。
◆ 感染性胃腸炎
感染性胃腸炎は多種多様の原因によるものを包含する症候群であるが、全国約3,000カ所の小児科定点からの患者発生報告数が増加するのは冬季であり、その大半はノロウイルスやロタウイルス等のウイルス感染が原因であると推測されている(IASR, Vol 24. No 12. p321-322参照)。また、患者発生のピークは例年12月の中旬以降となることが多く(図1)、その時期の感染性胃腸炎の、特に集団発生例の原因の多くはノロウイルスによるものであると推測される(感染症情報センターホームページhttp://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph-kj.html )。
ノロウイルス感染症の潜伏期間は数時間〜数日(平均1〜2日)で、主な症状は嘔気・嘔吐及び下痢であり、嘔吐・下痢は1日数回から多いときには10回以上のこともある。しかし、症状持続期間は数時間〜数日(平均1〜2日)と比較的短く、基礎疾患等の要因がない限りは、重症化して長期にわたり入院を要することは少ない。また、発熱の頻度は高くない。治療では特効薬はなく、対症療法となるが、最も重要なことは水分補給によって脱水を防ぐことである。
これまでノロウイルスの感染経路としては、食中毒としての経口感染がよく知られていたが、患者や無症状病原体保有者との直接的もしくは間接的な接触感染や、患者の嘔吐物や下痢便を介した飛沫感染等のヒト−ヒト感染があり、その感染力は非常に強い。また、昨年の東京都豊島区のホテルにおいて発生した集団感染事例のように、「吐物や下痢便の処理が適切に行われなかったために残存したウイルスを含む小粒子が、掃除などの物理的刺激によって舞い上がり、それを間近とは限らない場所で吸引し、経食道的に嚥下して消化管へ至る感染経路」である「塵埃感染」が発生する場合がある(感染症情報センターホームページ「ノロウイルスの感染経路」:http://idsc.nih.go.jp/disease/norovirus/0702keiro.html)。ノロウイルスの感染予防には、流水・石けんによる手洗いの励行と吐物や下痢便の適切な処理がきわめて重要である(感染症情報センターホームページ「家庭等一般の方々へ」:http://idsc.nih.go.jp/disease/norovirus/taio-a.html 、「医療従事者・施設スタッフ用」:http://idsc.nih.go.jp/disease/norovirus/taio-b.html )。
感染症発生動向調査によると、感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第42週以降増加が続いていたが、2007年第48週の定点当たり報告数は13.6(報告数41,003)であり、前週の報告数(定点当たり報告数9.0、報告数27,123)を大きく上回った(図1)。都道府県別では長崎県(34.7)、大分県(32.1)、佐賀県(29.0)、福岡県(26.7)、熊本県(26.2)、石川県(23.8)、鹿児島県(21.4)の順であり、九州地域の各県の報告数の増加が目立っている(図2)。発生報告数を年齢別にみると、0〜1歳24.1%、2〜3歳20.6%、4〜5歳16.8%の順であり、5歳以下で全報告数の60%前後を、7歳以下で70%以上を占めている(図3)のは例年と同様である。
1997年から2006年までの過去10年間において感染性胃腸炎の定点当たり報告数のピークの時期をみると、第50週が4回(1998年、1999年、2005年、2006年)、第51週が4回(1997年、2000年、2001年、2003年)、第49週が1回(2002年)、第52週が1回(2004年)の順となっており、全て第49〜52週の間に報告数がピークとなっている。2007年の感染性胃腸炎の報告数も、今後更に増加し、間もなくピークを迎えるものと予想される。感染性胃腸炎の発生動向の推移には、今後とも注意が必要である。
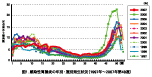 |
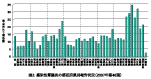 |
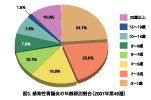 |
| 図1. 感染性胃腸炎の年別・週別発生状況(1997年〜2007年第48週) | 図2. 感染性胃腸炎の都道府県別報告状況(2007年第48週) | 図3. 感染性胃腸炎の年齢群別割合(2007年第48週) |
Copyright ©2004 Infectious Disease Surveillance Center All Rights Reserved. |